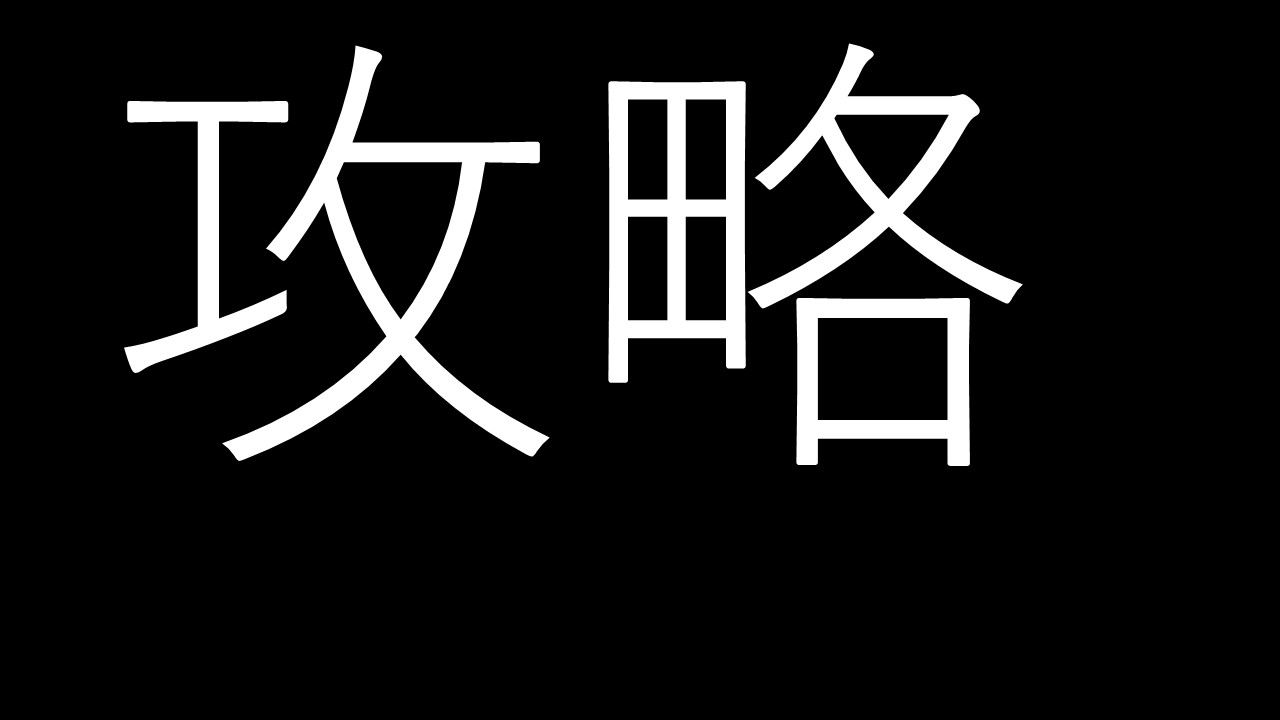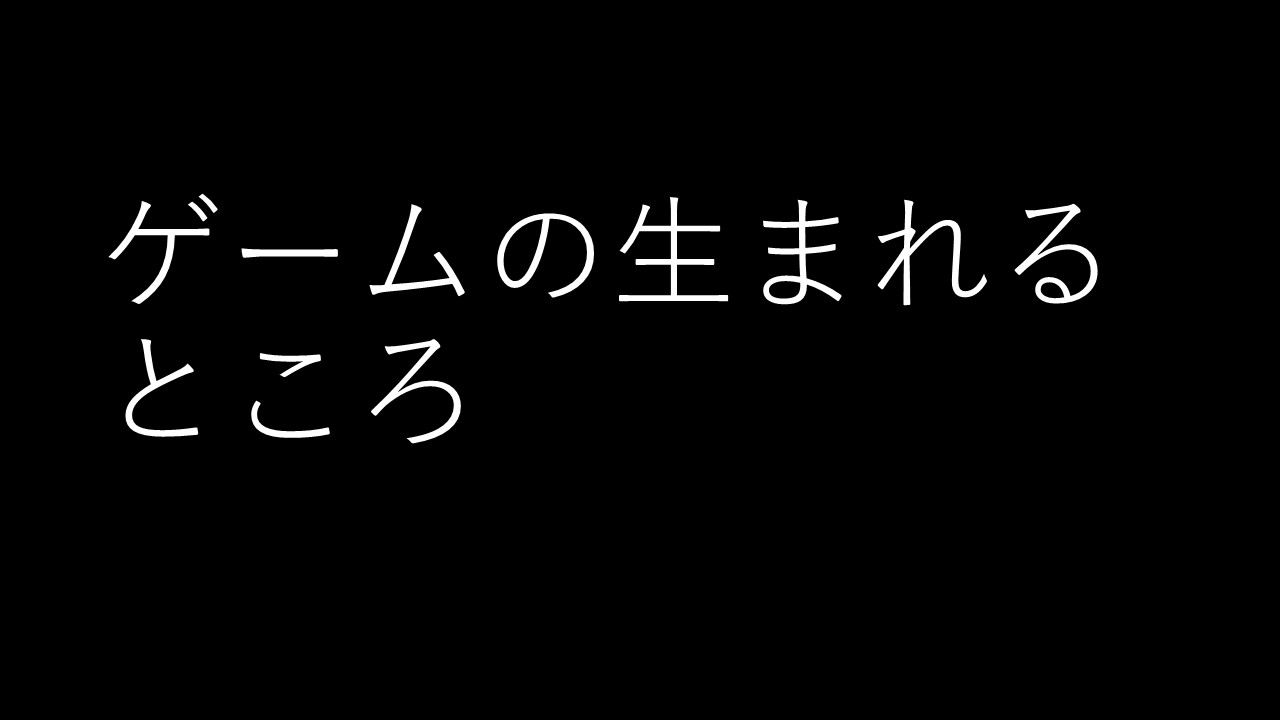This post is also available in: English (英語)
**Featured by the developer**
~本記事は、開発者様より御紹介を頂いた作品のレビューです。金銭的な提供は受けておらず、中立的な立場から執筆しています。~
インディーゲームをクリアしてはレビュー記事を書き綴る企画、IndieGame100の第二作。
今回は【STRANGER SAGA -流れ者バッチとイスキエルドの野望】を取り上げるぞ!
個人ゲーム開発者さんで創作のネタ探しに苦心していらっしゃる方から、面白いインディーゲームを探しているという方まで。
クリア後だからこそ言える、このゲームの素晴らしさと「あとちょっと‥‥‥!!!」なポイントを正直に伝えたい。
- 「シミュレーションゲームをサクサク遊ぶ」ことに徹底してこだわった設計が没入感◎
- 練り込まれた戦闘バランスがゲームの密度を引き上げる
- せっかくの「市民を育てるSRPG」という唯一無二のコンセプトの持つ可能性が、完全には発揮されていないのが歯痒い
じゃ、行きますよ!
ゲームの概要
ジャンル:SRPG
開発元: レトロゲームの手応えとバランスを追求するデザイン工房
パブリッシャー: レトロゲームの手応えとバランスを追求するデザイン工房
開発国: 日本
基本的なゲーム設計やUIに演出、戦闘の計算式などで、随所に『ファイアーエムブレム』シリーズへのオマージュが見られる作品。レジスタンス軍を率いて、強大な敵との熾烈で歯ごたえある戦いに身を投じていくことになる。
一介の市民である「シビリアン」を自分好みに成長させていくビルド要素もある。
リスペクト元を踏襲しつつも、今作独自の魅力としては、その「薄味」さが挙げられる。
詳しくは後述するが、UIやシナリオ、演出に戦闘の設計に至るまで、徹底して仕様のダイエットを行い、リスペクト元の魅力はそのままに、面倒くささや敷居の高さを極限までカットするという大胆なゲームデザインとなっている。
そのため、オマージュ元が言わば「こってりジューシー・重厚」路線だとすると、今作は明確に「あっさりサクサク・軽快」路線の軸で設計することで、差別化に成功している。
豊かさを削ることと紙一重なレベルでのスリム化を極限まで行ったことで、純粋に「シミュレーションゲームとしての面白さ」に全振りをした快作。
ちなみに筆者のプレイ時間はエンディングまで24時間54分だった。(データの検証やメモを取りながらのプレイだったので、実際のプレイ時間は長くても20時間くらいかと思われる。作者様によると10~15時間とのこと。)
SRPGをサクサク遊ばせるための工夫
本作には、SRPGをサクサク遊ばせるための仕掛けが随所にみられる。一つずつ見ていこう。
マップサイズのコンパクトさ

ニューゲームを開始した瞬間にちょっとした会話の後第一ステージが始まるのだが、よく見て欲しい。
ステージはこのウィンドウ内で全てだ。中盤までのステージは基本的に1ステージがスクロール無しでマップを見渡せるようにデザインされている。後半からはスクロールが必要なステージが出てくるものの、それでも一般的なSRPGの相場から見れば、かなり狭い。そのうえ、スクロールが必要な位置に、敵の移動範囲や攻撃範囲が来ないように、配置が工夫されている。
これが、筆者が思わず唸ったポイントだ。
SRPGをしていると、どうしても敵の移動範囲や攻撃範囲から逆算して作戦を組み立てる場面が出てくる。
そうした時に、マップが広いと何が起きるか?
延々とスクロールしては、 「あー、こっちだと攻撃範囲被るかぁ。じゃあ、あっちはどうだ?」 → スクロール → 「んー、こっちだと回復役の射程が足りないなぁ。別の壁役の移動範囲を見てみるか。」 → スクロール → ‥‥‥
と、延々とスクロールを続けてはマス目を確認する作業が発生する。言うまでもなく、この作業は「ゲーム的な楽しい思考」ではない。ただの”手間”だ。
「手間を極力無くして、本質的にゲームとして楽しい時間を提供するにはどうするか?」という、言われてみればごくごく当たり前のことに徹底してこだわったアプローチが、まず新鮮だった。
会話シーンが1ステージに1分あるかないかの短さ
ファイアーエムブレムシリーズしかり、ディスガイアシリーズしかり、スパロボしかり。SRPGは基本的に会話シーンによるストーリーテリングを非常に重視している。
これは操作キャラとプレイヤーとの一体感を肌で味わいやすいアクションゲームなどと違い、プレイヤーがどうしても作品世界に対して傍観者ポジションになってしまうSRPGにおいて、没入感を少しでも高めるための意図が多分にあるだろう。
STRANGER SAGAはここにもメスを入れた。
なんと、ステージ開始前の会話が一分未満、戦闘後の会話すら一言あるかないかという短さなのだ。
このテンポ間は本当に爆速としか言いようがなく、サクッと会話を見ては戦略的思考を楽しみ、そこから続く話もサクッと見てはまた新たなステージに挑み‥‥‥という形で、ゲームプレイに占める戦略的思考の時間が極めて長い。
想定プレイ時間が比較的短いながらも、Steamレビューでボリューム不足を訴える声が少ないのも、「ゲームとして操作・介入できる時間の割合が大きい」ことが大きな要因となっていそうだ。
あっさり&ボタンを押す必要のない演出
まずは見て頂くのが早いだろう。この動画を見て欲しい。
一切の演出の早送りをしていない。デフォルトでこのテンポ感である。
「遅くてまだるっこしい‥‥‥」
でも、
「早すぎて肉眼で捉えきれないッッ!!」
でもない。
理想的な演出の間は、白眉としか言いようがない。
しかも、である。この一連の「攻撃決定→戦闘演出→レベルアップ演出」中、筆者は一度もボタン操作を行っていない。
SRPGあるあるの、「戦闘演出のたびに決定ボタンを押さなければいけない問題」や「レベルアップのたびに派手なファンファーレをキャンセルしなければいけない問題」とは無縁だ。
ただ、画面構成を拝見した限りSRPG Studioでの制作と見られるので、もしかしたらそれのデフォルト機能なのかもしれない‥‥‥とは思わなくもない。有識者のご意見を伺いたいところ。
敵側のクリティカルが一部ボス以外発生しない設計
ダメージ計算式について考察した記事を掲載したところ、Xのフォロワー様から、
「そういえば、一度も敵のクリティカルを受けた記憶が無い‥‥‥」
とのご意見を頂戴した。
筆者もそれ以降、敵側のデータを注視しながらプレイしていたのだが、どうやら本当に敵側のクリティカルが発生しえないように、ステータスが設定されているらしいことを確認した。
この思い切りは本当にこのゲームの楽しさを底上げしている要素だ。
このゲームの主眼は「理詰めで部隊運用をしていく楽しさ」にある。敵のラッキーヒットで戦線崩壊するのは、運を乗りこなすカードゲームや、予想できない展開にハラハラするTRPGだからこそ成立する楽しさだ。今作の設計思想上の楽しさとは相いれない。
「このゲームだからこその楽しさ」を定義したうえで、「皆がやってるから自分もやる」という道を安易に取らない。
「よくある理不尽さ」を無くすことで、スムーズにテンポよく楽しむための導線を確保しているのは設計の妙と言える。
スキルを最小限に抑え、キャラのステータス成長率で個性を出すつくり
SRPGのトレンドはご多分に漏れず複雑化志向にあり、複数のスキルを組み合わせてコンボを狙う作りがデフォとなってきている。
その中でSTRANGER SAGAは、スキルの要素は最小限に、キャラのステータスの成長率で個性を出していく方式を取っている。
一番代表的なのは、アーチャーのルゲンツだろう。
彼はアーチャーとしては最低ラインの火力しかない代わりに、中衛ポジションと言っていいくらいの物理・魔法の防御力とHPを誇る。
そのため、普段は最低限の削りを行いつつ、いざという時に後衛キャラへの進路を身をもって塞ぎ、仲間を守るという、よくありそうでなかなか実例が思いつかないタイプの活躍をさせられる。
仕様をシンプルにすることで、リソースをバランス調整に一点集中させるという作りがキャラクターの個性からも見て取れる。
没入感をストーリーテリングや演出ではなく、ステージ量と密度で作り出す手法
今までに挙げたテンポ感やサクサク要素は、一つ一つは「快適性を上げる」ためのものだ。
このゲームの神髄は、快適性に特化することで、短時間のうちに大量の、高品質のステージを遊ばせ続けることで、「ゲームしてる時間が楽しい!」という体験を最大限生み出しているところにある。
練り込まれた戦闘バランス
“マップの狭さ”があることで部隊の連携が活きる
SRPGを一度でもやったことがある人なら、どこかの瞬間で間違いなくこの考えに至る。
「騎兵と飛行ユニットを量産して、機動力で圧倒すれば楽勝じゃね?」
というものだ。
だが、先述した通り、このゲームのマップは狭いのだ。そのうえ、マップ設計にも工夫が凝らされており、橋や通路、出入り口など、敵を分断する方法が豊富に用意されている。
敵側の火力も全体的に高めで、騎兵に単騎突撃させると返り討ちに合うことが結構ある。
そのため、自然と地形を生かして歩兵で蓋をするようにして敵を押しとどめ、後方から火力支援。厄介な搦め手をしてくる相手にはピンポイントで高機動力ユニットで強襲‥‥‥という、最高にSRPGしている瞬間に数多く立ち会うことになる。
スリム化の副産物がSRPG体験の濃密さに繋がっているのか、SRPGの面白さを追求した結果スリム化に行きついたのかは分からないが、本作特有の濃いSRPG体験は間違いなくマップの狭さが要因の一つだと思う。
弓と魔法の明確な性格分け
「遠隔攻撃」というくくりで似たような役割になりがちな弓と魔法に、明確な役割の差があるのも特徴的だ。
このゲームでは、弓の射程が3~5マス。魔法の射程が2~4マスが相場だ。(やたら射程の長いボウシューターや敵ボスもいるが、今回は単純化のため割愛する。)
どちらも隣接マスへの攻撃ができないため、懐に潜られると危険なのは同じだが、そこで射程の違いが響いてくる。
こちらの魔法がギリギリ届く距離は、たいていは敵の弓兵から一方的に攻撃されてしまう距離なのだ。
魔法ユニットは大火力の代償に往々にして脆いので、とにかく敵の攻撃範囲から逃げながら一撃を叩きこむ立ち回りが重要になる。
一方で弓兵は、抑えめな火力の割に耐久力が比較的高いことが多いうえに射程も長いので、雑に取り回しながら敵を削るのが主な役割になる。
こうした設計の違いが、「キャラを動かす」楽しさにダイレクトに繋がって来る。
ビルドで個性を出していく楽しさ
このゲームは「シビリアン」と呼ばれる市民たちを、強大な戦力へと押し上げていくことがキモの一つであるのだが、彼ら彼女らをどう育成するのか、非常に頭を悩ませることになる。

画像はシビリアンの中でも、攻撃的ステータスが抑えめな代わりに防御面が充実していて、必殺率が高いという特徴を持つセリアの最終ビルド。
物理・魔法両方の防御力に補正がかかるルーンランサーを選んだうえで装備も防御型にした結果、
物理と魔法の両方を受け切り、反撃回数の多さで必殺の発動試行回数を稼いで火力を補う
というビルドになった。
彼女は終盤に目覚ましい活躍を見せ、とりわけラストステージにて、敵の物理・魔法ユニット混成部隊を一人で引き受けながら着実に数を減らしていくという、いぶし銀の活躍を見せてくれた。
ここらへんの育成方針やキャラの使い勝手について、独断と偏見でTier表を作ってみたので、気になる方はご一読頂きたい。
「市民を育てるSRPG」である意味の薄さ
ここからは、ちょっと辛口になる。
筆者はこのゲームが好きだ。なんせ、既に4800文字も書いてるのだ。たぶん、ここまで語っている人間はそんなにいないだろう。だが、だからこそ気になった部分はやはりある。そこを作者様・ファンの皆様に失礼のない程度に正直に、書いていこうと思う。
市民を育てるSRPGという唯一性とシナリオが特に連動していない
最大の歯痒さポイントはここだ。
せっかくの「市民を育てる」という要素がほぼシナリオに絡んでこない。
ネタバレを避けると、「一介の農夫だった自分がまさかここまで来るとは‥‥‥」的な述懐を終盤にするキャラもいるにはいるが、その一言だけである。「一介の農夫だった」というスタート地点と「予想外のところまできた」というゴールは示されるが、その間のマイルストーンとなるイベントが何もない。
- 正規軍との実力差を前に挫折したり
- 人知れぬ努力のおかげで一目置かれるようになったり
- 「頼れる戦士」として扱われるのが当たり前になってしまって、「何でもないただの農民」として雑に扱ってくれる人がいなくなったことに一抹の寂しさを感じたり
- でも気心の知れた仲間だけは昔のまま接してくれて、自分の居場所を感じたり
といった、美味しいイベントが一切ない。
「一介の市民を育てるSRPG」で「強大な敵と戦っていく」となれば、そこで否が応にも期待してしまうのは、「戦士として成長していくサクセスストーリーの描写」だ。
前述したように、このゲームはゲーム性とテンポ感に全リソースをフルベットする勢いで注ぎ込んでおり、間違いなく面白い作品となっている。
そして、テンポ感を最大化するという目的のためには、シナリオ要素は極限まで削らなければ成立しないだろうとは思う。
しかしそれなら、「そもそも市民を育てる要素は必要なのか?」と思ってしまう。
ぶっちゃけこのゲーム性とシステムなら、「シビリアン」でなくとも「ノービス」や「すっぴん」等のゲーム的によくある用語でサラッと流すのでも十分に成立するのでは?という気がする。
まとめ:本格志向でありながら胃もたれしない気楽さ、ここにあります
いかがだっただろうか。
本当に些細な気になる点こそあれ、
気軽にガッツリ遊べるSRPG
として、限界までスリム化を図ることでプレイ感の純度と濃密さを高めに高めた作品だ。
プレイを考えているけど手が出なかった人、創作のアイディアに詰まっていた人の参考になれば幸い。
また、本当にありがたいことに、製作者のMSTさんとコンタクトを取ったところ、インタビュー記事を書かせて頂けることとなった。
MSTさんの余計なものを削ぎ落とす制作スタイルや、初めて作ったゲームに関するエピソードなどなど。
気になる方はリンクからどうぞ。
*次回予告*
次回のIndieGame100では、
Shiromofu FactoryさんのDungeon Antiquaをレビューしています。
んでは、良きゲーマーライフを!!
最後までお読み頂きありがとうございました!
前のIndieGame100レビュー “Splintered”
次のIndieGame100レビュー ”Dungeon Antiqua”
2025/11/10追記
本作の作者様ご本人にもレビュー記事をご覧頂き、温かいコメントを頂きました。
少しでも作品の意図に近づくことができていたならば、これに勝る喜びはありません。
*「Rasu」とは、この時のハンドルネームです。被りを防ぐために改名しました。*